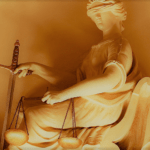洞窟の比喩
Allegory of the Cave
今回はちょっと、いや、だいぶ小難しい話になるかもしれません。まぁ僕が書いてるので小難しいとは言ってもタカが知れてますけど、哲学者プラトンを中心としたイデア論を基に書かれた『 国家 』と言う本から、本質と実体というお話。
まず プラトン(紀元前427年 – 紀元前347年)は言わずと知れた古代ギリシアの哲学者で、ソクラテスの弟子でありアリストテレスの師匠に当たります。イデアとはプラトン哲学の根本用語で本質や実像、また価値判断の基準となる永遠不変の価値などの意味を持ちます。
そして今回の「洞窟の比喩」は、そのイデア論を判りやすく説明するために『国家』第7巻に書き記したもので、要約するとこう書かれています。
地下の洞窟に住んでいる人々を想像してみよう。明かりに向かって洞窟の幅いっぱいの通路が入口まで達している。人々は子どもの頃から手足も首も縛られていて動くことができず、ずっと洞窟の奥を見ながら、振り返ることもできない。入口のはるか上方に火が燃えていて、人々をうしろから照らしている。火と人々の間に道があり、道に沿って低い壁が作られている。壁に沿って、いろんな種類の道具、木や石などで作られた人間や動物の像が、壁の上に差し上げられながら運ばれていく。運んでいく人々のなかには、声を出すものもいれば、黙っているものもいる。
洞窟に住む、手足の自由を奪われ洞窟の奥を眺めているのが僕たち人間です。そして僕たちが見ているのは「実体」ではなく「実体の影」ですが、僕たちはそれを「実体」だと思い込んで過ごしています。「実体」を運んで行く人々の声が洞窟の奥に反響して、この思い込みは確信へと変わっていきます。
つまり僕たちが日常的に見聞きしているさまざまな現実は、イデアの「影」に過ぎないとプラトンは考える、と言うことなのです。
洞窟で縛られて育った人間は、お互いに話すことはできます。そんな環境で育った人間は実体を見たことがない訳ですから当然、影つまり偽物を実体つまり本物だと思うでしょう。これが一般民衆だとプラトンは例えています。
『国家』と言う本は政治家を育て、国家をどう運営していくかと言う大きなテーマを持った内容なので、ところどころに民衆や大衆、政治家と言う言葉が出てきますが、これは会社やグループなどの運営にも共通することなので読み替えて説明します。
話を戻しますが、この洞窟の中の1人の縄を解いて洞窟の外へと連れ出し、明るい太陽の下で地上の全てを見せます。はじめは明るさに目が眩んで何も見えませんが徐々に目が慣れてくると実体がハッキリと見えてきてにわかには信じ難い光景を目にします。同時に、これまで見てきたものすべてが「実体の影」だった事に愕然とする筈です。
外に出た者は真実のすばらしさに驚き、それをもっともっと見たいと思うでしょう。むしろそう思う方が自然でしょう。しかしプラトンはこう主張しています。
外に出てイデアを目にした者は、また洞窟に舞い戻って前と同じ場所での生活に戻りたいと思うだろうか。普通は思わないだろう。でも戻るべきなのだ。前と同じ場所に戻って、何も知らない民衆に自分が見てきたイデアを語り伝える。それが為政者(いせいしゃ=政治家)の仕事なのだ。
政治家に必要な素質だと説いていますが、政治家に限らず組織を運営していく立場の人や指導者だったら、同じ理屈が通用するでしょう。現代社会でも自分の見聞きした情報を共有するのは有効な手段です。洞窟から唯一、実体を目にした者は、他の者よりも一つ多く経験をしたわけです。自分の経験を組織の運営に役立てるのが先人の役目だと言うのはその通りだと思います。
自分が見聞きしたものは全体の一部を見聞きしたに過ぎません。洞窟から出て世界は広がったとしても、それはさらなる大きな洞窟の中なのかもしれません。実体を見たと思っても、それは実体の影だったのかもしれないのです。
一人でそのまま突き進むには、新世界はあまりに壮大過ぎる。元に戻って経験したことをみんなに伝え、新世界を想像できる者だけが洞窟の外に出て、新世界での経験値を増やし、また経験してきたことを洞窟で話して次の世代につないでいくという繰り返しこそが、組織運営にとっては重要なんじゃないかと思うわけです。
ちなみにこの後、洞窟に戻って見てきたもの、体感したものを洞窟のみんなに話しますが、信じてはもらえずに疎外されてしまいます。これも組織でよくあることですね。人を動かすのは難しい。
洞窟の比喩
というお話でした。
~ 本文で紹介された書籍をご紹介 ~
You Might Also Like

ゲツコーギルド合同会社 CEO兼プロデューサー
2016年に東京下町から瀬戸内の離島に移住。クリエイターの働き方や人財育成、再生、地域でのクリエイティブやICTを活用したブランディングや地域創生、事業再生を得意としたプロデュースやディレクションで活躍中。メガネ&広島弁や伊予弁など方言女子が大好物。個人的には懐古的なモノがスキ。ネガティブ属性だがユーモアを忘れない。1970年 江戸下町産。